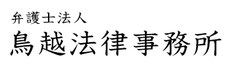最近の労使間トラブルに関する裁判例
裁判例29:起訴休職期間満了による解雇の有効性
大阪地方裁判所平成29年9月25日判決(判例タイムズ1447号129頁)
本件は、国立大学法人(被告)の助教として勤務していた原告が、傷害致死の被疑事実により逮捕され(後に、暴行罪で判決確定)、その後、起訴され、被告の起訴休職規定に基づき、休職となった後、2年間の起訴休職期間満了により解雇されたところ、その無効を主張して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事案である。
大阪地方裁判所は、以下のとおり判示し、原告の請求を棄却した。
一般に、労働者が起訴された場合、勾留等の事情により、当該労働者が物理的に労務の継続的給付ができなくなる場合があるほか、勾留されなかった場合でも、犯罪の嫌疑が客観化した当該労働者を業務に従事させることにより、使用者の対外的信用が失墜し、職場秩序の維持に障害が生じるおそれがある場合には、事実上、労務提供をさせることができなくなる。起訴休職制度は、このように、自己都合によって、物理的又は事実上労務の提供ができない状態に至った労働者につき、短期間でその状態が解消される可能性もあることから、直ちに労働契約を終了させるのではなく、一定期間、休職とすることで使用者の上記不利益を回避しつつ、解雇を猶予して労働者を保護することを目的とするものであると解される。
以上のような起訴休職制度の趣旨に鑑みれば、使用者は、労務の提供ができない状態が短期間で解消されない場合についてまで、当該労働者との労働契約の継続を余儀なくされるべき理由はないから、不当に短い期間でない限り、就業規則において、起訴休職期間に上限を設けることができると解するのが相当である。
起訴休職期間の上限を2年間とする本件上限規定は、合理的な内容であると認められ、本件解雇には客観的に合理的な理由があり、社会通念上の相当性もあると認めるのが相当である。